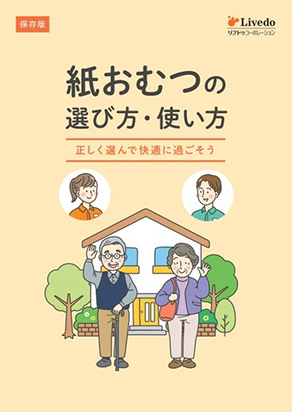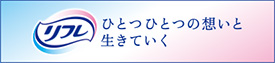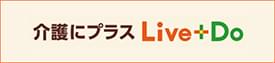前田慶子氏コラム〈3/3〉

- 前田慶子(まえだけいこ)氏
東京慈恵会医科大学附属病院看護部師長
慈恵看護専門学校卒業後、慈恵会医科大学附属病院に入職。
摂食嚥下障害看護認定看護師
整形外科病棟の看護師長時に、栄養サポートチーム専任看護師に従事し、ここでの患者様との出会いをきっかけに、摂食・嚥下障害看護認定看護師を目指す。
現在は、摂食嚥下支援チームや看護師長として、外来・病棟看護師と連携を取りながら日々多くの患者様の食への支援をしています。
患者様の栄養管理や食べたいと思える口腔内環境をつくれるように、日々多職種と連携しながら臨床で学びを深めております。
4. どのような種類の食具があるのか、どのように選び・使うのか
持ち方・握り方など利用する際の効果、注意点
病気や障害、加齢など様々な状況が生じても「生きる力」を引き出し、機能低下や動作困難を助けてくれる道具は「自助具:self-help device」と呼ばれる。
ここでの自助具とは、日常生活で必要な作業を可能な限り自分で行えるように捕食動作を支援し自分のペースで美味しくご飯が食べられるようにサポートする福祉用具である。
特に食具では「箸」「スプーン」「フォーク」「滑り止めマット」「皿」「茶碗」などがあり、選択の際は「グリップの素材・質感、形状や重さ」「口にあたる部分の食べやすさや」「口に運びやすい角度」など自身にあったものの選択が重要となる。