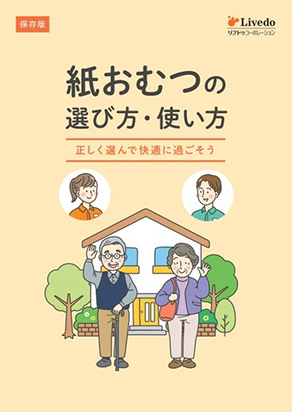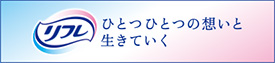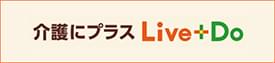矢吹知之氏コラム〈2/3〉

- 矢吹 知之(やぶき ともゆき)氏
高知県立大学社会福祉学部 教授
アルツハイマーカフェの創始者べレ・ミーセン氏に師事。認知症の人のピアサポートの場「おれんじドア実行委員」を務める。専門は社会学、社会福祉学、認知症介護
(特に介護家族支援)。認知症とともに生きる社会をつくり育むための研究をしている。
認知症とともに生きるためには、認知症を治す、予防することに注視するだけではなく、社会が変わることを伝え、当事者から学び当事者とともに考える実践に基づく研究を行っている。
認知症の人と家族どちらにも偏らない関わりや支援とは何かを考え続けている。
3.不適切なケアの背景にある気持ちと解決策
1)多忙さからくる「焦り」
●「人手が足りないからやむを得ない」という想い
介護業界の有効求人倍率は他業種と比べて非常に高く、慢性的な人材不足が続いています。入浴介助の日に、認知症の人に何度も呼び止められ「わたしはどうしてここにいるのかしら。ここにいなくちゃいけないのかしら」などと繰り返し質問されることがあります。その時、忙しさからつい「大丈夫ですよ。心配ないですよ」とその場をやり過ごすような対応をしてしまいました。
ある人は、部屋に設置してあるコールボタンで呼び出し、職員が部屋に慌てて訪問すると「何でもない」と言います。一日何度も繰り返すために、呼び出されても顔だけ見てドアを閉めるようにしました。
これらの背景には「焦り」の感情があります。職員は、特定の利用者に時間を費やし続けることで、その日の業務が滞り、他の利用者への対応が疎かになることを懸念しています。そのため、「焦り」から「やむを得ない」と感じるようになってしまうのです。